浄化槽に入浴剤はだめ?おすすめ&悪影響のある成分など詳しく紹介

浄化槽を使用している場合、浄化槽に影響があってはいけないとして、入浴剤の使用を控えている家庭もあることと思います。
浄化槽の機能を低下させる成分はいくつかありますが、入浴剤の中には悪影響のある成分が含まれている場合があります。
この記事では、浄化槽は入浴剤を使ってはだめなのか、そもそも浄化槽に流してはいけない成分にはどのようなものがあるのか、逆におすすめできる成分などを紹介します。
浄化槽を大切に使用したい人、でもたまには温泉みたいなお風呂に入りたい人は、参考にしてください。
目次
浄化槽で入浴剤を使用するときの注意点
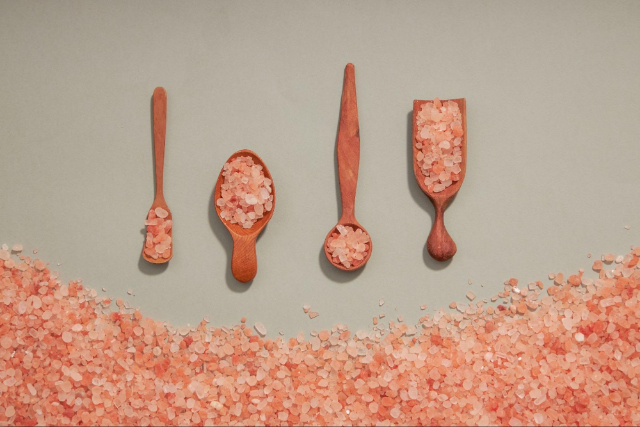
浄化槽を設置している家庭での入浴剤の使用は、適量を守れば基本的には問題はありませんが、いくつかの注意点があります。
浄化槽のある家庭での入浴剤の使い方を紹介します。
入浴剤の使用量を守って使用する
入浴剤には、浄化槽に流入する量が多すぎると浄化槽内の微生物の処理能力が低下する成分が含まれている場合があります。
例えば保温効果の高い入浴剤は無機塩類を主成分とし、特にバスソルトなどは温浴効果が高いとされています。
浄化槽に塩類濃度が濃い溶液が流れ込むと、微生物の細胞が破壊されてしまいますが、決められた使用量に従って使用していれば問題はありません。
浄化槽を使用している場合、入浴剤は適量に抑えて楽しみましょう。
色が着いている入浴剤は検査の妨げになる場合も
入浴剤には色がついていたり白濁していたりするものなど、色や質感の種類が豊富にありますが、水質検査において異常が確認しづらくなる場合があります。
浄化槽の水質検査では、放流水(外へ排出する浄化済みの処理水)のpHを測定した際にピンク色の結果が出れば正常な水質と判断されます。
有色の入浴剤は色の判断がつきづらくなり、白濁している入浴剤は透明度を低下させるため、水質検査で正確な結果が出せず、管理を難しくする場合があります。
適切な量を心がけて使用するには心配ありませんが、過剰にならないよう注意しましょう。
硫黄成分の入った入浴剤は微生物が死滅する
湯の華など、温泉入浴剤は酸性の強い硫黄成分の入ったものがあり、微生物の働きが弱まり、死滅させてしまうなど、浄化槽の機能が低下します。
また、硫黄は濃度が高くなるとリン酸鉄からリンを溶出させ、放流水中のリン濃度を高めます。
リン濃度の高い放流水は富栄養化といって、それを栄養とするアオコや赤潮が異常発生し、水中の酸素が不足して水質が悪化する事態を招いてしまいます。
硫黄成分が含まれる入浴剤は、使用を避けてください。
米ぬかや日本酒の入浴剤はBOD濃度が高くなる
入浴剤に入っている成分で米ぬかや日本酒がありますが、これらは有機物のため排水のBOD濃度が高くなります。
BODとは、有機物(汚れ)をエサにする微生物の呼吸に必要な酸素量のことで、この数値が高い(濃度が高い)ほど、水質が悪化していることを示します。
米ぬかも日本酒も美肌効果があり、血行や新陳代謝も良くなるといわれていますが、浄化槽にとっては処理機能の低下に繋がる成分のため、使用の際は適量に抑えましょう。
浄化槽の微生物に悪影響があるもの

入浴剤以外にも、浄化槽には流してはいけないものがあります。
浄化槽の微生物の活動に悪影響があるものを紹介します。
塩素系漂白剤の大量使用
カビ取り剤や台所用漂白剤、パイプクリーナーなどの塩素系漂白剤は、殺菌作用が高いため、浄化槽内の微生物に悪影響を与えます。
大量に使用すると微生物が死滅したり働きが悪くなってしまうため、通常使用の範囲内にとどめ、過剰に使用しないようにしましょう。
→浄化槽に使える洗剤と使えない洗剤とは?バイオを強化する方法を解説
洗剤の大量使用
浄化槽を設置している家庭では、洗剤を使用する際はなるべく中性のものを選び、使い過ぎることなく適量で使用しましょう。
台所やトイレ・浴室など、家の中には洗剤を使用する場所が複数ありますが、上でも紹介した通り、酸性に傾くことは微生物の働きが弱まるため避けましょう。
もし中性の洗剤がない場合は、弱酸性または弱アルカリ性のものを使用し、何を使用する場合でもメーカーの指示量を守りましょう。
一度に大量の排水
一度に大量の排水を行うと、浄化の不十分な水が放流されてしまう可能性があるため、使う時間帯を分ける・2回に分けるなど、量を調節して排水するようにしましょう。
特に洗濯機と浴槽の水は量が多いため、時間帯をずらして使用するようにしてください。
塩
入浴剤のケースでも紹介しましたが、塩類溶液や塩水などを多量に流すと微生物が死滅する可能性があります。
入浴剤に含まれる程度の塩類濃度なら問題ありませんが、あまり塩分が高いと浄化槽はおろか肌にも負担がかかります。
バスソルトは、塩の種類によっては少量でも濃度の濃いものがあります。
浴槽を傷める・追い炊きができないなど、他にも問題が発生する可能性があるため、塩には十分気をつけましょう。
油
浄化槽の微生物は油の分解が苦手であり、排水パイプが詰まる原因にもなるため、食用油などは排水口から捨ててはいけません。
油に混ぜて排水口から流して捨てられる処理剤がありますが、浄化槽の中で再び油と水に分離して元の状態に戻ってしまうため、処理剤を利用して流すのも避けてください。
できればお皿やフライパンなどについた油もキッチンペーパーなどで拭き取ってから洗うのが理想です。
→シンクに油を流してしまった!浄化槽に油を流してはいけない理由と対処法
食材などのゴミ
浄化槽は流れてきたすべての有機ゴミを引き受けられるようにはできていないため、野菜や食材のゴミなどは流さないようにしましょう。
微生物にとっても能力やスペースに限界があり、処理しきれずに浄化槽内で詰まりの原因となる場合があるため、ネットなどを使用して食材ゴミや燃えるゴミとして捨てましょう。
たばこの吸い殻など
たばこの吸い殻や、吸い殻を浸けていた水(たばこ廃液)などは浄化槽に流すことで微生物に悪影響を及ぼします。
たばこの吸い殻は水に溶けないため、浄化槽に流すと微生物には分解できず、たばこ廃液は微生物を死滅させてしまいます。
水に溶けないティッシュや紙おむつなどは浄化槽にとっては異物ですが、たばこも異物であり、有害薬剤と同等のものであると認識して、流してしまわないよう十分気をつけましょう。
浄化槽への使用をすすめるもの

浄化槽への使用をおすすめしたい洗剤・薬剤などを紹介します。
微生物の働きを助ける成分、害を与えない成分もあります。ぜひ参考にしてください。
無添加の洗剤
微生物は生き物であることを考えると、無添加の洗剤は適しているでしょう。
通常、洗剤には以下のような成分が含まれています。
- 石油系合成界面活性剤
- 蛍光増白剤
- 漂白剤
- 合成香料
- 着色料
- 抗菌剤など
これらは通常量での使用は問題ありませんが、無添加洗剤はこれらが入っていないため、使い過ぎを気にする必要がありません。
無添加洗剤なら、微生物にとって居心地の良い環境を整えることができるでしょう。
酵素系の入浴剤
酵素系の入浴剤は、皮膚に刺激を与えずに綺麗にし、やはり入浴効果を高める働きもあります。
パパインやパンクレアチン・タンパク質分解酵素などの成分を含んだ、無添加の酵素系入浴剤を選べばより浄化槽に安心です。
酵素入りの洗浄液・消臭剤
浄化槽の微生物に悪影響を与えず、活性化する効果のある洗浄液や消臭剤があります。
株式会社スリーケーの「排水管洗浄液」と「浄化槽汲み取りトイレ消臭剤」はどちらも酵素による効果が期待できる製品のため、浄化槽の微生物のことを考えたときにおすすめです。
「排水管洗浄液」は排水口から流し込んで使用しますが、排水口から排水管内の汚れを落とし、汚れの再付着の予防も期待できるため日々のお掃除に適しています。
大学との共同研究においても、浄化槽内の微生物に良い影響を与えるという結果が得られている洗浄液です。
「浄化槽汲み取りトイレ消臭剤」は浄化槽の臭いに困ったときに使用しますが、微生物の働きを助ける補助剤としても使用でき、その方法はトイレから流すだけです。
浄化槽には基本的に土壌中の微生物を投入しますが、「浄化槽汲み取りトイレ消臭剤」にも同様に土壌中の微生物が含まれています。
まとめ
浄化槽の中では微生物が一生懸命排水を浄化してくれているため、できるだけ居心地をよくしたいと思えば、入浴剤ひとつとっても使用の影響が気になります。
指示量に従う、硫黄は避ける、有機物の入っていないものを選ぶなど、入浴剤についてはそれほど使い分けも難しくなく、意外と楽しめることが分かって頂けたかと思います。
株式会社スリーケーの「排水管洗浄液」と「浄化槽汲み取りトイレ消臭剤」を利用して、いつでも浄化槽が元気に稼働できる環境を整えて、温泉気分を楽しみながらも、浄化槽を大切に使いましょう。
「排水管洗浄液」はこちらから、「浄化槽汲み取りトイレ消臭剤」はこちらからお買い求め頂けます。
