浄化槽のBODが高いとどうなる?原因や改善方法・検査の重要性を紹介

浄化槽を使用していると時々耳にする『BOD』。
BODは浄化槽から放流される処理水の水質がどのような状態であるのかが分かる値です。
この記事では、BODによって何が判明するのか、値が高い場合の影響や改善方法、検査の重要性などを紹介します。
浄化槽の使用方法の見直しや定期的な検査に関係するBODについて、理解を深めましょう。
目次
BODとは?
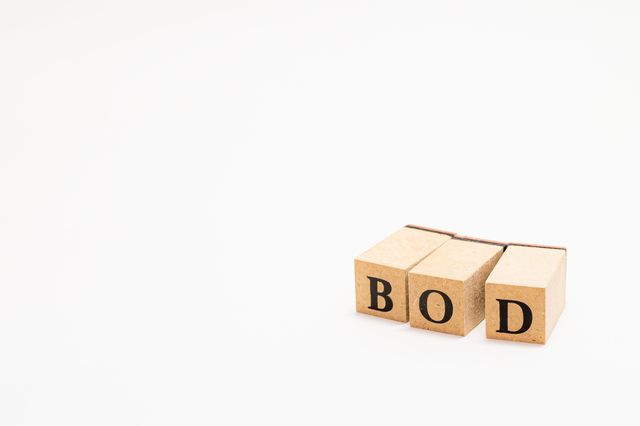
浄化槽の処理水は、外部へ放流するに値する水質まで浄化できているのかがさまざまな測定で判明する値によって分かりますが、BODもそのひとつです。
まずはBODとは何かを紹介します。
水がどれくらい汚れているかを示す値
BODの正式名称は『Biochemical Oxygen Demand(生物化学的酸素要求量)』で、有機性の汚れをどの程度含む水質であるかを示す値のことです。
水に含まれる汚れ(有機物)を微生物が分解する際、水中に含まれる酸素が必要です。
汚れが多ければ必要とされる酸素量が多くなるためBODは高くなり、汚れていない水は微生物の酸素消費量が少なく済むためBODが低くなります。
BODは法定検査で分かる値
浄化槽の定期検査は法定検査と保守点検がありますが、BODの検査は浄化槽の法定検査で行われます。
法定検査では、現場で行う検査と処理水を持ち帰って行う検査とがありますが、BOD検査は持ち帰って5日間かけて行う検査のため、現場では結果が出ません。
そのため、検査の結果は検査日から1週間〜10日後くらいに郵送で届きます。
浄化槽のBODの基準値
浄化槽には、放流していい処理水のBOD濃度と、性能としてのBOD除去率の、基準値がそれぞれ定められています。
浄化槽の種類 | 放流水のBOD濃度の基準 | 浄化槽のBOD除去率の基準 |
|---|---|---|
単独浄化槽 | 90mg/L以下 | 65%以上 |
合併浄化槽 | 20mg/L以下 | 90%以上 |
単独浄化槽はトイレの汚水のみを高い能力で浄化しますが、時代に伴い生活雑排水の汚れが環境の水質汚濁の原因として高割合になってきました。
今は合併浄化槽の設置が義務付けられ、単独浄化槽から合併浄化槽への転換が推進されています。
浄化槽のBODが高いとは?

「BODが高い」とは、微生物が水中にある有機物(汚れ)を分解するために必要となる酸素の量が多いことを表しています。
つまり、水が汚れているほど、BODは高くなります。
ここでは、浄化槽のBODが高い場合の、原因や起こりうる問題、改善方法を紹介します。
浄化槽のBODが高い原因
浄化槽のBODが高いのは、有機汚れの多い生活雑排水を浄化槽使用者が多く流していることが原因です。
私達が生活していて頻繁に排水口から流すものの量と、5mg/L以下のBOD(魚が棲める水質)まで薄めるのに必要な水の量の一例は以下です。
使用済み天ぷら油 20mL | 6,000L |
マヨネーズ大さじ1 15mL | 3,900L |
牛乳コップ1杯 200mL | 3,300L |
ビールコップ1杯 180mL | 3,000L |
味噌汁お椀1杯 180mL | 1,410L |
米のとぎ汁 500mL | 1,200L |
中濃ソース大さじ1 15mL | 390L |
シャンプー1回分 4.5mL | 201L |
台所用洗剤1回分 4.5mL | 201L |
(参考:『環境省 生活排水読本』)
1Lは大きなペットボトルでよく見かけますが、例えば中濃ソース大さじ1は、ペットボトル390本分の水で薄めなければ魚が棲めません。
そして、浄化槽のBODを検査する場合、検査対象の採水は消毒槽又は消毒タンクに入る直前の処理水から行われます。
そのため、法定検査でBODの基準をクリアするためには、微生物による汚れの分解を終えた、消毒する前の時点で基準値である必要があります。
浄化槽のBODが高いということは、微生物が有機物を分解しても高い数値が出てしまうほど汚れた水を浄化槽に排出しているか、浄化槽の能力が落ちているかのどちらかでしょう。
浄化槽のBODが高いとどうなる?
浄化槽のBODが高いと、基準値を満たせない汚れた水を放流することになるため、周囲の水環境に悪影響を与えてしまいます。
BODの値が高い水の放流が続くと、水環境に悪影響を与える以下のような赤潮やアオコが発生する原因となります。
赤潮 | アオコ |
|---|---|
|
|
赤潮やアオコが発生する理由は、生活排水に豊富に含まれる有機物・窒素やリンが、プランクトンや藻の豊富な栄養となる『富栄養化』になるためです。
浄化槽のBODが高い場合、このような環境汚染につながってしまいます。
浄化槽のBODを改善するには

高いBODを基準値に下げるには、生活するうえで排水に気をつけることや浄化槽の機能上の効率化を計ることなどがあります。
点検や検査の結果、プロに相談することで他にもできる対策はありますが、家庭においてもできるだけ処理水をきれいにする努力をしましょう。
排水するものの成分に気をつける
排水するものに以下のものが多く含まれていると、BODが高くなることがあります。
- 油分
- 海面活性成分(洗剤)
- 甘味料・調味料
- アルコール類
- 合成着色料
生活するうえで全てを排除することは難しいものばかりです。
しかし、料理の洗い物の際には油分やソースなどを拭き取ってから洗う、飲み切れる・食べきれる量に抑えるなど、ちょっとした心配りをしてみましょう。
→シンクに油を流してしまった!浄化槽に油を流してはいけない理由と対処法
排水量の変化に気をつける
排水量が増えると、汚れた水を多く排水することになるため、BODが上がる場合があります。
また、排水量が集中して増える時間帯があると、浄化槽に負荷がかかり、性能が落ちる原因となります。
そのため、洗濯と入浴の時間をずらすなどの工夫が必要です。
浄化槽への排水量は一人平均200L/日といわれています。BODに影響が出るほど排水量が多くなってしまう場合は、状況に合わせて浄化槽を交換する必要があるかもしれません。
微生物が生活しやすい環境を整える
微生物が弱ってしまうと浄化槽の処理能力が低下するため、微生物が棲みやすい環境を整えて、汚れの分解を促進しましょう。
例えば、微生物にとっての適温は15〜30℃のため、夏は高すぎないよう、冬は低すぎないように、温度調整が必要です。
また、掃除の際に漂白剤や殺菌剤を使用する場合、使い過ぎると微生物が弱ったり減ったり、死滅する場合などがあるため、強い洗剤を使う際の量や頻度には注意しましょう。
ブロアの風量調整をする
BODが高い場合は微生物が酸欠状態になるため、ブロアの風量を上げることで微生物に空気を送り込み、汚水を攪拌・循環することで処理の効率も上がります。
ブロアの風量だけでなく、異音がしたり不具合があったりしないか、快適に作動しているかどうかの確認も大切です。
→浄化槽ブロアの故障をそのままにしてはいけない理由とは?対処法を紹介
BODを好物とする好気性微生物を増やす
BODは、好気性微生物が有機物を分解する際に必要とする酸素の量であるため、好気性微生物を増やすことによって、BODの改善が期待できます。
浄化槽の中には酸素の必要な好気性微生物と酸素がいらない嫌気性微生物が、汚水を分解・浄化しています。
この微生物を増やしたり補充したりすることで、浄化槽の機能回復や微生物の活性化が図れます。
バクテリアの補充液や活性剤は市販のものがありますが、浄化槽管理士や点検時の業者などに相談してみましょう。
→浄化槽のバクテリアの補充方法は?不足して起こる問題や予防法を紹介
法定検査・保守点検をしっかり受ける

浄化槽のBODを基準値に抑えるためには、法定検査や保守点検をしっかり受けて、稼働状況や生活が浄化槽に与えている影響などを把握し、正しく使用する必要があります。
BODの測定は以下の法定検査時に行います。
- 法第7条検査……浄化槽の新設(使い始め)から3ヶ月を経過した日から5ヶ月間
- 法第11条法定検査……毎年1回。保守点検を受けていないと受けられない
法定検査は保守点検の結果を合わせて提出することで受けることができます。
また、法定検査は浄化槽を清掃して水を張った状態で受けなければいけません。
浄化槽を正しくきれいに使用して性能を低下させないことが、BODを基準値にとどめ、水環境を守ることにつながります。
→浄化槽の点検回数は何回?点検と検査の違いは?正しい頻度で浄化槽を大切に
まとめ
浄化槽のBODについて、値が高い場合の原因や改善方法、検査の重要性を紹介しました。
浄化槽のBODを基準値に抑えるためには、微生物のことを考えた洗剤や消臭剤の使用がおすすめです。
→浄化槽に使える洗剤と使えない洗剤とは?バイオを強化する方法を解説
株式会社スリーケーの『排水管洗浄液』と『浄化槽汲み取りトイレ消臭剤』は、どちらも微生物の酵素が効果を発揮。
微生物に悪影響を与えず、普段から微生物にとって居心地のいい環境を整えられるため、おすすめです。水環境を住まいから守りましょう。
『浄化槽汲み取りトイレ消臭剤』はこちらからどうぞ。
